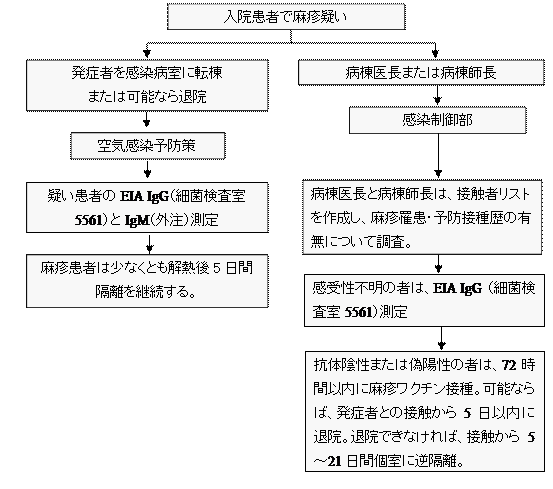|
空気予防策および接触予防策、飛沫予防策を行う。 潜伏期は多くは8~12日であり、最短7日から最長21日である。 発熱、咳嗽、鼻汁、結膜充血、眼脂などのカタル症状で始まり、発熱3日目頃から頬粘膜の白色粘膜疹(Koplik斑)がみられ、全身発疹が出現する。 発症1~2日前から解熱後3日まで感染力がある。 基本再生産数(R0)が6~21と、感染症のなかで最も強い感染力があり、予防策の徹底が必要である。 |
|
|
|
フローチャート |
|
|
|
1.
入院患者で麻疹発症が疑われた場合 |
|
診断した医師は、リスクマネージャーへすぐに連絡し、リスクマネージャーは、感染制御部へ連絡する(夜間は当直師長へ連絡)。 |
|
1)
当該患者は可能ならすみやかに退院させるか、感染病室に転棟させる。 2)
感染病室に空室がない場合は、可能な限り麻疹患者を優先するよう調整を試みるが、不可能な場合、一般病床個室に隔離し空気予防策をとる。ただし感受性者や免疫不全者の病室から可能な限り距離をおくこと。 3)
小児科病棟では感受性のある小児が多いため、個室隔離でも伝播する危険が多く、感染病室が不可能な場合は、他の病棟で個室隔離を行う。 4)
一般病棟個室は他病室と空調を共有しているため、通気口はダンボール等で塞ぐ。部屋の扉は開閉時以外は常時閉め、換気は窓を開けて行なう。 5)
隔離患者の管理ついて · 患者は室外で行う検査は原則として行わない。 · エックス線撮影、採血等も部屋で行い、トイレは室内のものを用いる。 · 部屋の消毒、食器、リネンの特別な対策は不要であり、通常で良い。 · 面会は最小限にし、麻疹に対する免疫がない者の面会は禁止する。 · 麻疹に免疫のあるものはマスクの着用の必要はない。 · 麻疹に免疫のない医療従事者は立ち入らない。 6)
複数の麻疹患者を同室に収容することは可能である。(コホーティング) 7)
麻疹患者は少なくとも解熱後5日間隔離を継続する。 8)
同じ病棟内の入院患者全員の罹患歴と予防接種歴を確認する。空気感染であるため、直接的接触がない場合でも全員への対応が必要となる。麻疹患者の発症2日前からの接触者リストを作り、感受性者の有無について調査する。医療従事者についても接触者に免疫があることを確認する。 9)
接触者の麻疹に対する免疫保有が不明の場合、麻疹IgG(EIA法)を測定する。 10) 上記接触者で麻疹抗体が陰性または偽陽性の者は、72時間以内に麻疹ワクチン接種を行う。また可能ならば、発症者との接触から5日以内に退院させる。退院できなければ、接触から5~21日間陰圧病室や感染病室に隔離する。 11) 免疫不全者には、ワクチンは接種禁忌であるため、6日以内であれば、γグロブリンの投与を検討する。生物製剤であり十分な説明と文書による同意が必要である。 12) 医療従事者で発症の危険がある場合は、接触から5~21日間自宅待機すること。 |
|
|
|
2.
職員の麻疹発症が疑われた場合 |
|
診断した医師は、リスクマネージャーへすぐに連絡し、リスクマネージャーは感染制御部へ連絡する(夜間は当直師長へ連絡)。 |
|
1)
ただちに自宅待機とし、他の医療機関を受診する際は、あらかじめ電話連絡をすること。 2)
接触者のリストアップを行い、1. 7)~11)と同様に対処する。 3)
麻疹と診断された職員は、発疹出現後7日間(または解熱後3日間)の休務とする。 |
|
|
|
1.
患者が直接受付を受診した場合 |
|
1)
時間内(受付窓口及び医務課対応) |
|
①
鼻汁・咳などの症状がある患者にはマスク(通常用)を渡す(咳エチケット)。 ②
麻疹患者との接触があったことの申し出があった場合は、患者にサージカルマスクを着用してもらい、受付窓口へ案内する。 ③
受付窓口での応対は麻疹の抗体陽性が確認された職員が担当する。 ④
医療サービス係(5143)は内科外来(5731,5732)看護師長に連絡の上、内科外来看護師を呼び対応を依頼する。(15歳未満の小児患者の場合は小児科外来(5787)へ連絡する) ⑤
内科(小児科)外来看護師は、感染症外来へ患者を速やかに案内する。 ⑥
感染症外来が使用されている場合は、トリアージ施設を使用する。 ⑦
感染症外来・トリアージ施設ともに使用できない場合は、医務課に連絡の上、医療相談室に案内する。 ⑧
医療安全管理係(6847)は麻疹疑い患者が来院したことを、感染制御部(5708)に連絡する。 ⑨
麻疹に対する免疫を持たない者、もしくは免疫が不明な者との接触があった場合は、その時点でICTと協議の上、対策を講じる。 |
|
2)
時間外受診(土、日、祭日を含む)(事務当直者対応) |
|
①
事務当直者は、患者にサージカルマスクを着用してもらう。(当直者が麻疹の抗体がない場合はN95マスク着用) ②
事務当直者は、受付処理後、感染症外来に患者を案内する。 ③
事務当直者は麻疹疑い患者が来院したことを、救急科医師に連絡する。 ④
診察医師は、麻疹が否定できない場合は、翌日感染制御部へ連絡する。患者が帰宅する際は、麻疹に対する免疫がない者との接触を避けるように指導すること。 ⑤
当直師長は、麻疹を否定できない場合は、翌日感染制御部へ連絡する。 ⑥
麻疹に対する免疫を持たない者、もしくは免疫が不明な者との接触が院内であった場合は、その時点で感染制御部と協議の上、対策を講じる。 |
|
2.
各外来で麻疹(疑い)患者が判明した場合 |
|
①
麻疹(疑い)患者を認めた医師・看護師は、外来師長(小児は小児科外来看護師)に連絡し、感染症外来を確保する。 ②
担当看護師は、感染症外来へ患者を速やかに案内する。 ③
感染症外来が使用されている場合は、トリアージ施設を使用する。 ④
感染症外来・トリアージ施設ともに使用できない場合は、医務課に連絡の上、医療相談室に案内する。 ⑤
外来師長または小児科外来看護師は麻疹疑い患者が来院したことを、感染制御部、医療安全管理係(6847)に連絡する。 ⑥
麻疹に対する免疫を持たない者、もしくは免疫が不明な者との接触が院内であった場合は、その時点で感染制御部と協議の上、対策を講じる。 |
|
3.
電話連絡の場合 |
|
時間内は総合診療当番医(小児の場合は小児科外来医師)が応対、時間外は救急科が応対し、当院は特定機能病院であり、免疫不全者も多いことを説明の上、可能な限り他院での受診を勧める。受診する場合は、感染症外来を確保した上で来院時間を設定し、受付事務窓口(時間内5143、時間外5195)へ電話を転送、感染症外来外扉から感染症外来へ案内できるように準備する。 |
|
4.
入院が必要となった場合 |
|
①
感染症病室に入院させる。 ②
上記が確保できない場合は、他院への紹介を検討する。 ③
一般病棟への入室は可能な限り避ける。 |
|
|