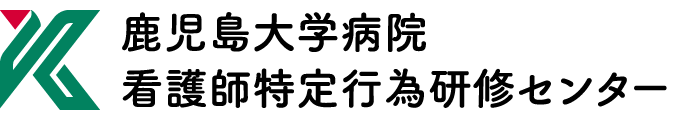特定行為における看護師の研修制度とは?
「特定行為に係る看護師の研修制度」の変遷
「特定行為に係る看護師の研修制度」は平成27年10月に「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の一部として施行されました。この法律は平成21年から厚生労働省で話し合いが行われてきました。
その中で看護師の名称が変わっています。
看護師特定行為研修制度の変遷
| 年 | 会議名 | 看護師の名称 |
|---|---|---|
| 平成21年 | 規制改革会議 | NP(ナースプラクティショナー) |
| 平成22年 | チーム医療推進に関する検討委員会 | 特定看護師(仮称) |
| 平成23年 | チーム医療推進会議「看護師特定能力認証制度」 | 特定能力を認証された看護師 |
| 平成25年 | チーム医療推進会議「看護師特定能力認証制度」 | 指定された研修を受けた看護師(看護師籍に登録) |
| 平成27年 | 指定された研修を受けた看護師(「看護師籍に登録」が削除され「指定研修機関から厚労省に届ける」となった) | |
| 平成28年 | 特定行為研修を修了した看護師 |
特定行為が選出された流れ
チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループの看護業務(203項目)実態調査で、臨床で働いている医師・看護師に対し実際に看護師が行っている業務の調査を行いました。この調査結果を受けてチーム医療推進会議で臨床で行われている看護師業務を保助看法5条の「診療の補助」範囲にあてはまるかどうかを検討しました。医行為A~E(右図)に分類されています。これを参考に特定行為が決定されました。
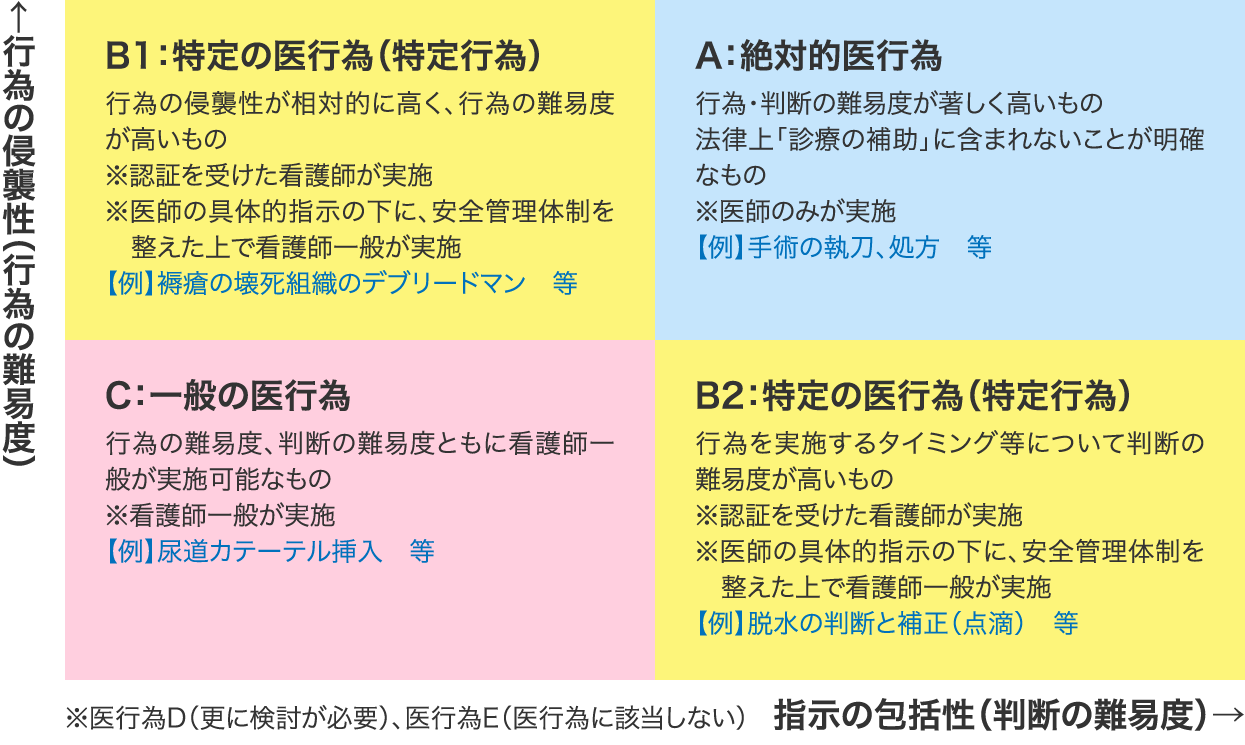
特定行為に係る看護師の研修制度
話し合いの中で「特定行為」とは、医師又は歯科医師の指示の下、臨床に係る実践的かつ高度な理解力、思考力、判断力その他の能力をもって行わなければ、衛生上危害を生ずるおそれのある行為と考えられました。特定行為を実施するためには、おおむね3~5年の臨床経験があり、更にその分野の追加教育を受けた看護師、又はそれと同等の看護師が実施することが望ましいとされました。この「追加教育」の部分が「特定行為に係る看護師の研修制度」になりました。
研修内容は共通科目と区分別科目に分かれそれぞれに時間数が決められています。共通科目を受講、合格した後に区分別科目を受講、合格し指定研修機関から修了認定されると修了証が発行されます。
共通科目
| 共通科目の内容 | 時間数 |
|---|---|
| 臨床病態生理学 | 30 |
| 臨床推論 | 45 |
| フィジカルアセスメント | 45 |
| 臨床薬理学 | 45 |
| 疾病・臨床病態概論 | 40 |
| 医療安全学/特定行為実践 | 45 |
| 合計 | 250 |
区分別科目(講義+演習の時間数)
| 特定行為区分 | 時間数 | 特定行為区分 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 9 | 創傷管理関連 | 34 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 29 | 創部ドレーン管理関連 | 5 |
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 8 | 動脈血液ガス分析関連 | 13 |
| 循環器関連 | 20 | 透析管理関連 | 11 |
| 心嚢ドレーン管理関連 | 8 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 16 |
| 胸腔ドレーン管理関連 | 13 | 感染に係る薬剤投与関連 | 29 |
| 腹腔ドレーン管理関連 | 8 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 16 |
| ろう孔管理関連 | 22 | 術後疼痛管理関連 | 8 |
| 栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル 管理)関連 |
7 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | 28 |
| 栄養に係るカテーテル管理 (末梢留置型中心静脈注射用 カテーテル管理)関連 |
8 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 26 |
| 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 17 |
※各行為ごとに5症例の経験が必要