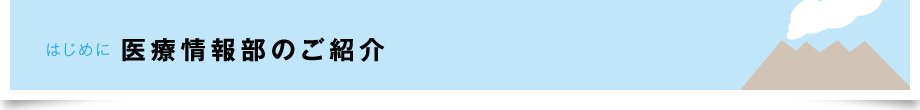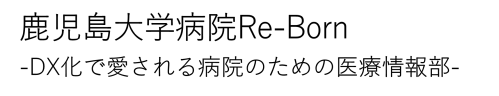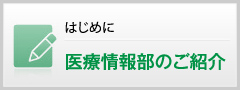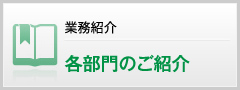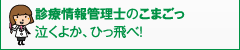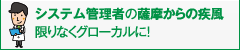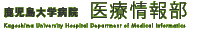医療情報部長 大石 充
2025年4月より鹿児島大学病院医療情報部長を拝命した大石充です。歴史と伝統のある鹿児島大学病院医療情報部を新たなステージへ導くことができればと思っています。
鹿児島大学病院医療情報部の歴史は古く、1984年に国立大学病院としては初めて“オーダーリングシステム”を構築しました。その後時代のニーズを的確に捉えて、病院機能改善のための現状分析やシステム開発⇒標準化、パッケージ化⇒安定した運用支援+蓄積データの二次利用への支援と医療情報部の役割を更新してきました。さらに病院経営上の意思決定に必要なデータの抽出や編集加工および医療クラークの教育・管理などといったマンとマシーンの「コミュニケーション」(共同)性を具体的に進めてまいりました。このような改革・進化は全国からも注目され、新型コロナ禍に負けることなく高い収益性を得られる大学病院へと進化をさせていきました。
近年、AI(Artificial Intelligence)やICT(Information and Communication Techonology)・IoT(Internet of Things)などの多くの技術革新が医療の現場に導入されつつあり、病院だけでなく医療そのものを大きく変えようとしています。このDX化の大きなうねりに対処するために医療情報部は“マン”に当たる医療クラークの管理・教育業務を医療クラーク管理室へと移譲させて、システム管理と医療情報管理に特化した部門へと進化を遂げることになりました。病院DX化担当副病院長と医療情報部長の二つ重積に任命されたことは、医療情報部が中心となって病院DX化を進めることを託されたことに他ならないと考えております。離島を多く抱える鹿児島の最後の砦としての鹿児島大学病院が、ICTやIoTを屈指して遠隔医療のDX化の模範となれるように改革していきたいと思います。さらにAIと実臨牀を融合させてワークシフト・ワークシェアリングと医療安全との両立を図り、若い医療従事者が好んで集まって、地元鹿児島県民のよりどころとなれるような鹿児島大学病院の礎を築いていければと思っております。
医療情報に関してはまだまだ“ひよっこ”ですが、皆に愛される鹿児島大学病院となるためにDX化や医療情報をキーワードに貢献してまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
医療情報部長 大石 充