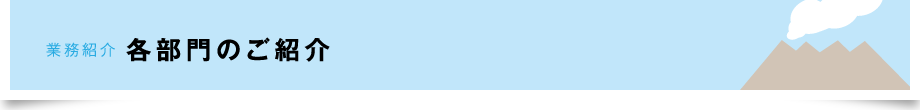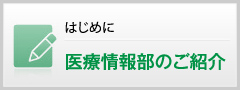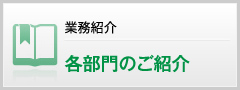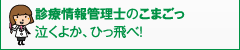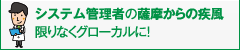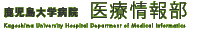システム開発/運用
THINK(Total Hospital Information System of Kagoshima University)
Since December 1983~
鹿児島大学医学部附属病院では、将来にわたる医療サービスの向上をめざした新しい病院づくりを推進する為に、1983年12月より医師、看護師などが発生源で情報を入出力するという新しい運用形態を開発しました。このオーダリングシステムによる鹿児島大学総合病院情報システムをTHINKと命名しました。
THINKは、全員参加型という積極的なシステム構築が特徴です。医師による病名登録システムを皮切りに、処方・注射オーダリングシステムなど各種オーダリングシステムをはじめ、看護システム、物流システム、手術オーダリングシステムなどのサブシステムを次々に開発し、安定した稼働実績をあげるようになりました。ちなみに、「オーダリングシステム」という呼称は、鹿児島大学病院発です。
Since January 2001~
2001年1月よりクライアント・サーバ型のシステムへ移行するとともに、過去の膨大な蓄積データを有効活用するツールを開発しました。それが、病院データウェアハウス(Data Warehouse: DWH)と呼ばれる大規模データベースです。蓄積された情報を迅速に参照できる、あるいは迅速・簡便に抽出・分析できる基盤を構築しました。このDWHを用いて、DPCBANKシステム(DPCごと患者ごと1入院ごとの収支が把握できるオンラインシステム)、病院管理会計システム等の開発を行いました。これらのシステムの安定稼働により、各部門間の情報共有がさらに進み、正確なデータ利用や参照がより簡便に行えるようになり、診療関連業務の効率化、患者サービスの充実、さらに病院経営の健全化に多大に寄与するようになりました。
Since October 2006~
2006年10月から、患者記録の電子化を契機に「e-kanja記録システム」という本院独自の電子カルテ機能を開発し、診療記録の質的充実を図ってきました。これは、POS(Problem Oriented System: 患者さんの視点に立ってその患者さんの問題を解決するためのシステムで問題志向型システムと呼ばれる)に基づくもので、入力支援機能より、登録した診療記録の参照、検索機能の充実に力点を置いたユニークな電子患者記録システムです。このシステムによって、院内のEHR(Electronic Health Record)化を推進する一方で、地域医療連携の基盤ともなるITKarteを導入し、病病連携、病診連携の推進とともに、患者・家族とのコミュニケーションツールの確立を目指しています。
Since March 2012~
2012年3月より、電子指示システムの開発を行っています。医療安全対策等、患者さんをはじめとする国民の信頼が得られる医療の提供が求められる一方で、診療の高度化、専門化に伴い、指示の内容も複雑多岐に渡り、その量も加速的に増加しています。
しかし、これまでの病院情報システム開発の過程において、電子指示システムの開発は遅れていました。指示のシステム化の取り組みは、ワープロ機能を用いて、医師から看護師に対してフリーテキストで指示内容を伝える方法がこれまで一般的でした。
この方法では、指示に対する実施入力が、医事会計や診療記録へ反映されません。当院が目指している電子指示システムとは、全ての指示がオーダと連携し、指示に対する実施入力により医事会計への取り込み、医師記録や看護記録との連動を目指し、効率性や確実性を担保出来ることを目指しています。
また、電子指示システムの最終ゴールとして、電子クリティカルパスに焦点を当てて開発を進めています。
Since April 2013~
今後は、これまでに培ってきた本院の情報基盤の機能強化及び拡充を図るとともに、診療情報の精度管理、質的充実を目指し、更なる効率化と医療安全の向上を実現していきたいと考えています。また、大学病院の特性を生かした地域医療連携システムの確立に向けて、中長期的ビジョンを掲げ、着実に歩を進めていきたいと願っています。
THINKが目指す中長期的ビジョンとは、「チーム医療」を推進する機能を電子カルテシステムで具現化することです。もうすぐご報告できるかと思います。乞うご期待!!