
看護活動の紹介
1.鹿児島大学病院看護部の地域支援体制
看護部は急性期病院の看護師としてのミッションとして、地域貢献・社会貢献に対して4つを掲げています。
地域貢献・社会貢献
地域における看護の質向上
地域医療を支える看護職の資質の向上
地域医療ネットワークの構築によるシームレスな医療・看護の提供
災害医療ネットワーク
2. 鹿児島県「地域における訪問看護師等人材育成支援事業」への参加
地域医療介護総合確保基金を活用した、「地域における訪問看護師等人材育成事業」を県からの委託事業として平成26年から30年の5年間実施しました。地域看護コース看護師や専門・特定・認定看護師等を県内各地に派遣し、医療介護者対象の研修、患者・家族・住民対象の講話、多職種合同カンファレンス、同行訪問を行いました。特に28年度以降は医療資源の少ない離島・へき地からの依頼が6割以上を占め、多くの住民や医療関係者からも高評価をもらい、病院で学べない多くのことを地域の皆様から学び看護の原点を考えるいい機会となっています。
| 事業内容 | テーマ |
|---|---|
| 患者・家族・住民対象講話 |
|
| 医療・介護職を対象とした研修 |
|
| 多職種合同カンファレンス 同行訪問 |
|
実施例
| 日置市 | 多職種連携研修会アドバンス・ケア・プランニングについて (緩和ケア認定看護師・地域看護コース看護師) |
|---|---|
| 徳之島(天城町・徳之島町) | 看護・介護職員のための摂食・嚥下研修会 (摂食嚥下看護認定看護師・地域看護コース看護師) |
| 喜界町 | 高齢者のスキンケアとおむつケア WOC領域の専門的なケアを必要とする利用者への同行訪問 (皮膚排泄ケア認定看護師・地域看護コース看護師) |
| 南種子町 | 誤嚥や窒息予防に対するリスク管理 (脳卒中認定看護師・地域看護コース看護師) |
3.鹿児島県「助産師出向支援モデル事業」への参加
鹿児島県は助産師の地域偏在があり、鹿児島市内を除いては助産師不足の現状があります。安心で安全な出産環境を整備するためには助産師の地域偏在を補うとともに助産師の実践能力の強化支援を図ることが重要です。そのため「鹿児島県助産師出向支援モデル事業」が設置され、当院は出向施設として、地域で厳しい状況にある地域助産施設へ中堅助産師が平成26年9月より出向しております。出向助産師は、受け入れ施設の丁寧な準備の中、環境の違いを受け止めながら業務を担っています。今後、助産師自身のキャリアアップへの期待、互いの部署が抱える様々な課題の共有など、多様な側面からの効果が期待できるものと考えます。
4.地域分娩施設との人事交流
当病棟は年間約240件の分娩がありますが、異常分娩が9割を占め、正常分娩が1割です。助産師にとって「やりがい」「生きがい」は分娩の経験から形成されるものであり、特に新人助産師にとって分娩を経験することはキャリア形成していくうえでも重要と考えます。そこで、平成24年9月より当院からは地域の助産施設に新人看護師が正常分娩の実施研修、地域施設からはNICU研修を受けるなど施設間の人事交流を実施しています。

地域施設での新人助産師の正常分娩実施研修

地域分娩施設からNICU研修
5.地域施設との管理者の人事交流
統合周産期医療を担う地域施設と管理者人事交流を平成26年8月より開始しました。特定機能病院で33~34週以降の早産児、先天性疾患を持つ新生児の診療が中心の当院と、全国的にも、高度な新生児に医療に担っている地域施設の新生児センターの管理者が、周産期医療の連携、ネットワーク作りの構築、NICU看護の実践教育及び管理体制の在り方、地域との連携について互いに学ぶ機会となっています。
6.地域施設へ短期派遣
地域施設から看護の質の向上・スタッフ教育の目的での派遣の依頼があり、平成28年・30年種子島医療センターに皮膚排泄ケア看護認定看護師等を派遣しました。医療センターでは、外来・入院患者の人工肛門や褥瘡・創傷の直接ケアや褥瘡委員会の支援、地域医療従事者対象の講演会などを行っています。本院の派遣した看護師にとっても1週間滞在していたからこそ、現状の問題点を分析し、施設にあった方法を一緒に検討することができいい学びになりました。
7.三島村看護師派遣
有人離島を数多く抱える鹿児島県では、その地域の方々の健康管理を支援する医療スタッフを確保することが課題となっています。
平成25年度鹿児島大学病院は、三島村の要請を受けて看護師派遣の協定を結びました。現在まで2人の派遣に留まっていますが、地域医療・看護に貢献できるように”自ら輝く鹿児島看護職キャリアパス”における”地域看護コース”等、地域看護に貢献できる看護師育成に努めています。
8.離島巡回診療
毎年県の要請を受け、地域の病院と協力し、年7~8回、1泊2日~3泊4日の日程で参加しています。 本土の病院へのアクセスが悪い島の生活において、疾病の予防に努めることは極めて重要であり、少しでも島での保健活動に貢献できたらと考えています。 施設での看護しか経験のない看護師にとって、この離島巡回診療への参加は、ライフサポーターとしての役割を認識する機会となっています。

三島村(竹島・硫黄島・黒島):耳鼻咽喉科
ICU 中野圭菜
私は、三島村巡回診療に鹿児島赤十字病院スタッフ、役場保健師や医師に同行し参加しました。島民は、医師の常駐がなくすぐに病院を受診できない環境の中で、多くの不安を抱きながら生活していることがわかりました。診療所の看護師は、島民一人一人と話しをしながら思いに寄り添い、生活する上で「今何に困っているか・必要なことは何か」を把握し島民の代弁者として関わっていました。島での看護師の関わりで大事なことは、健康を維持するための「予防的な関わり」だと思いました。
私たちは急性期治療に携わっており、特に私は集中治療室に勤務しているため、患者の退院前や退院後の生活を見据えながら関わることが十分にできていないと感じています。しかし、今回巡回診療に参加したことで、患者が住み慣れた地域でその人らしく生活することすることの大切さを改めて学ぶことができました。今後も病院看護師と地域看護師で連携しチームケアを行っていくことが必要であり、私たちに求められていることだと思います。島の自然や島民の温かさに触れながら、離島の医療環境だけでなく、生活環境も実際に見て感じることができ、大変貴重な経験となりました。

巡回診療スタッフの皆さんと

竹島診療所
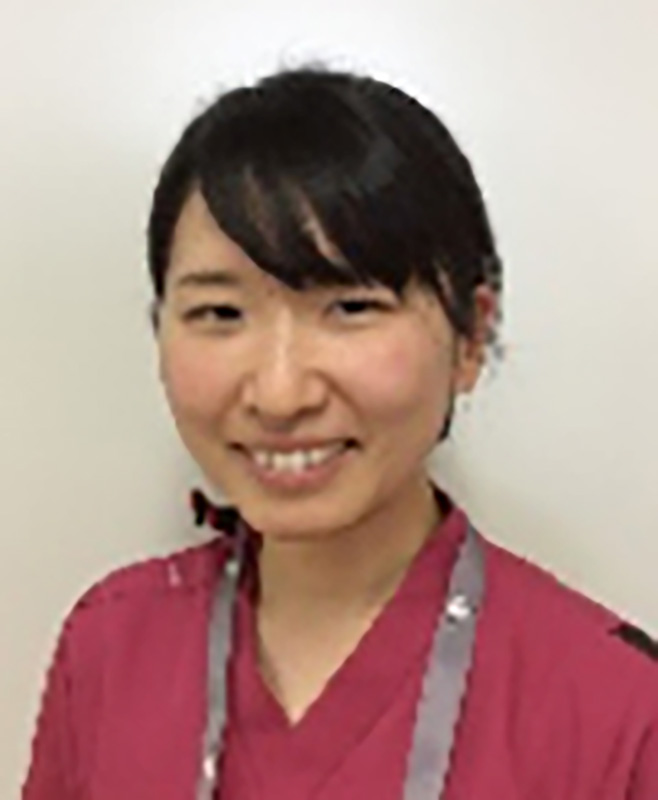
十島村(悪石島・子宝島・宝島):眼科
手術部 内山彩音
今回、十島村の巡回診療に参加し、眼科の一般診療や学校検診に携わることができました。
十島村を訪れるのは今回が初めてでしたが、自然がとても豊かで、島民の方々同士のつながりが強い印象を受けました。離島の環境を自分の目で見て、現地の看護師や島民の方々から話を聞く中で、離島では医療資源が限られていますが、各島の看護師が医師や役場の看護師と連携し、島民の健康管理をするために様々な工夫をされていることを学びました。私は現在手術室で勤務していますが、手術を受けた患者さんが、再び住み慣れた環境で生活することを見据えた関わりが必要であることを再認識することができました。

道路を歩く牛

宝島の壁画
9.災害支援
DMAT Disaster Medical Assistance Team
大規模災害や傷病者が多数発生した事故などの現場で、急性期に活動できる専門的訓練を受けた医療チーム(医師・看護師・事務職員で構成)です。当院は2チームのDMATが指定されており、看護師4名がチームに加わっています。国の広域医療搬送訓練やDMAT技能維持訓練等に参加しながらスキルを磨き、要請があれば直ちに出動します。日頃は、BLS研修や災害看護研修などで、看護師教育・指導も行っています。


DMAT実働訓練
災害支援登録ナース(院内)
災害発生時の「多数傷病者受け入れ」の際に専門的知識・技術をもって災害救護活動を実施します。平成22年度から院内認定としてスタートしました。現在、20名の看護師が登録されており、院内での災害訓練をはじめ、鹿児島市多数傷病者事故救急訓練や鹿児島県総合防災訓練などにも参加しています。

災害支援登録ナース院内認定バッジ

院内災害訓練でのトリアージ訓練

エアーストレッチャーによる移送訓練

看護師を対象とした災害支援登録
ナースの自主企画によるトリアージ訓練
10.地域医療連携センター
地域医療連携センターでは、ベッドコントロール(空床一元管理)、前方支援、後方支援、相談業務を担っています。
医師、メディカルソーシャルワーカー、管理栄養士、事務職員等の多職種が協働し、患者さんの入院前から退院後までの安心・安全な療養生活を支えるために頑張っています。

地域医療連携センター

入院支援室