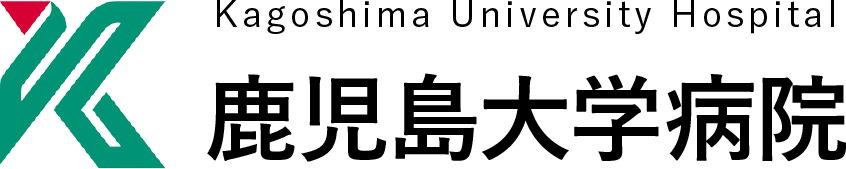7月25日(日)に、鹿児島大学病院で「人工呼吸器・ECMO研修会」が開催され、36名の医療従事者が参加しました。
この研修会は、COVID-19の重症例に対する人工呼吸器/ECMO管理について、同治療を有効かつ安全に実施可能な人材育成を目的に、医師・看護師・臨床工学技士を対象に行われたものです。
ECMO(エクモ、Extracorporeal membrane oxygenation:体外式膜型人工肺)は、機能が低下した肺の代わりに体内へ酸素を取り込む働きをする医療機器で、親指ほどの管を太ももの血管から入れて体外へ血液を抜き出し、二酸化炭素を拡散・除去した上で酸素を加え、首付近の血管から体内に戻す装置です。
この間、患者さんは肺を休めることができますが、回復には2週間以上かかることもあり、治療中は24時間態勢での管理が求められます。
そのため、熟練した「医療チーム」が必要となり、医師・看護師・臨床工学技士で構成されたチームが本格的な実践練習を行いました。
なお、今回は理学療法士も初めて参加し、チューブに繋がれた患者さん(人形)の体位変換について、介助の手順も確認しました。
また、研修会の後半では、垣花 泰之 救命救急センター長による講義も行われ、参加者はメモを取りながら、終始熱心に聴講していました。
当日は、KTS鹿児島テレビから取材の申込みがあり、「医療チーム」の必要性や実践練習の様子について、インタビューや撮影が併せて行われました。
鹿児島大学病院は、鹿児島県における医療の「最後の砦」を守るためにも、引き続き一致団結して医療に取り組んでまいります。

(人形)の太ももの血管から入れる様子

(人形)の体位変換を行う様子


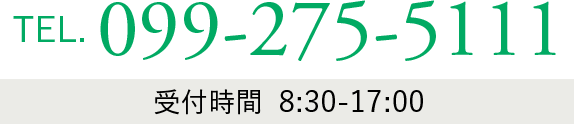
 HOME
HOME 病院紹介
病院紹介 受診される方へ
受診される方へ 医療関係者の方へ
医療関係者の方へ 診療科案内
診療科案内 部門案内
部門案内 よくある質問
よくある質問 お問合せ
お問合せ アクセス・駐車場
アクセス・駐車場