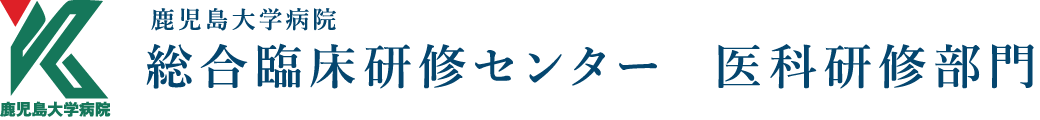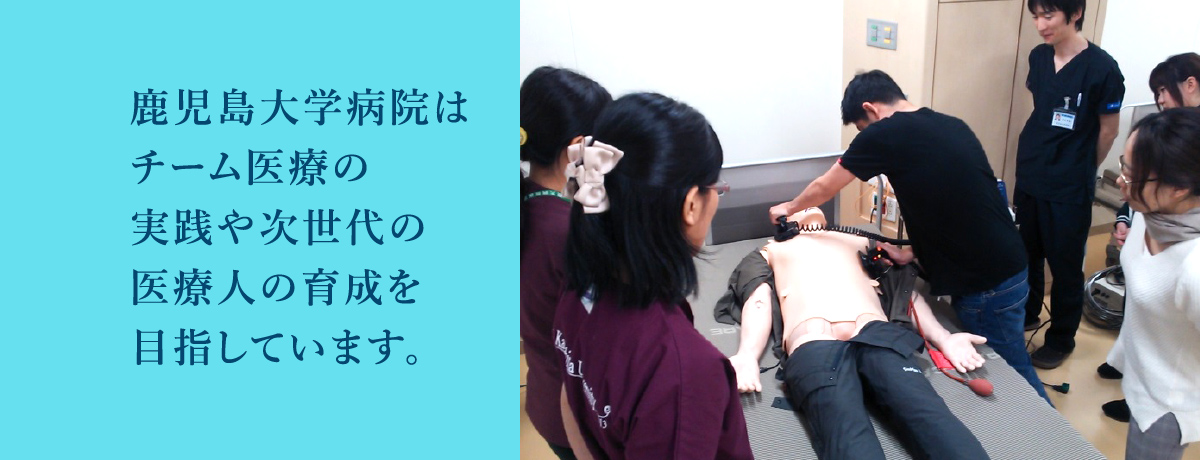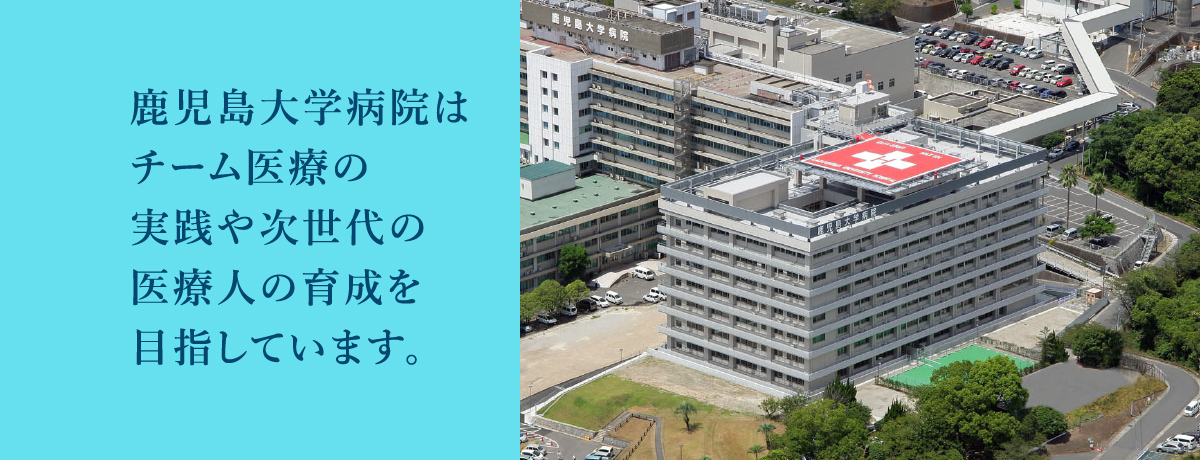医師としてのはじめの一歩
鹿児島大学病院「桜島」プログラム1年目初期臨床研修医
私は大学病院での半年間の研修生活を経て,現在は奄美大島にある県立大島病院で研修医として働いております。離島の, しかも第一線病院であることもあって, 患者数は多く,慌ただしく日々が過ぎています。大学病院との大きな違いは救急搬送があること, ドクターの数に比べて患者数が多く入れ替わりが激しいこと, 紙カルテであることでしょうか。症例数が多く, いわゆるCommon disease を経験できることは間違いありません。救急の現場を目の当たりにすることも大学病院では稀でしょう。パソコンでのカルテ入力に慣れていたため, 手書きでのカルテ記載は非常に難しく感じてしまいます。何せ「コピペ」も「修正」も「保存」もできませんから。よほど頭の中の整理がついていないと, きれいなわかりやすいカルテは書き得ません。大学病院にはなかったものがここにはたくさんあります。ただ一つ言えるのは, 大学病院での半年間はとても充実したものだったと強く思えるということです。
最初の半年間で強く感じたのは, 学生時代の勉強が如何に医療とかけ離れていたかということでした。ある患者から得られた身体所見, 既往歴, 血液検査の結果などあれこれ書いてある文章の中から, 必要なキーワードを抽出し, 疾患を特定する。国家試験のときはキーワードをうまく繋ぐことさえできれば正解に辿りつくことができたように思います。しかし現実は違う。患者を前に必要な質問をし, 身体所見を正確にとり, 適切な検査を適切なタイミングで行わなければ正解に辿り着くことなんて到底できません。闇雲にやればいいというものでもない。正解があるとも限らない。さまざまな患者がいる。常に客観性を持って柔軟な頭でものごとを捉えて行かねばならない。机上の勉強と実際の現場との大きな違いである。ある所見をどのように捉え,どう解釈し, 次に何をする必要があるか, 一人一人の患者に時間がかけられる大学病院での研修だったからこそ, この作業にじっくり時間を注げたのだと思います。また, 医師としての道を歩み出したばかりのこの時期に,ものごとを順序立てて, 論理的に考える「クセ」をつけることの大切さを実感できたことは, 医師としての礎を築く上で大変貴重な経験だったと思います。
未だに「先生」と呼ばれることには慣れませんが, 少しずつ自分が医師であることには慣れてきた気がします。医者を続けることに不安を感じることもありましたが, 医者にしか味わえない幸せを感じる場面もありました。まだまだ未熟で医師としての自覚も欠けている私ですが, この先も自分らしく, 楽しく医師としての人生を歩んで行きたいと思います。
研修の様子