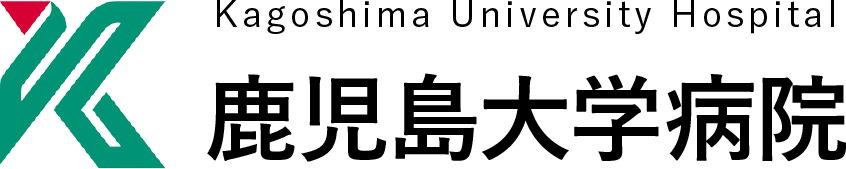テスト1
テスト1の紹介
認知症疾患医療センター運営事業の概要
国内の認知症者数は、国の推計で令和7年には高齢者の5人に1人にあたる約700万人に達すると予想されています。さらに軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)者数を加えると、約1,300万人にも及ぶといわれており、認知症対策は国の重要な課題の一つとなっています。
認知症疾患医療センターは、認知症の早期診断、早期対応のための体制の充実を図るため、国・県を挙げて整備が推進されており、保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断とその初期対応、認知症の行動・心理症状(Behavioral and psychological symptoms of dementia -BPSD)と身体合併症の急性期治療に関する対応、専門医療相談、診断後の相談支援等を実施しています。地域において認知症の進行予防から地域生活の維持まで、必要となる医療を提供できる機能体制の構築を図る目的があり、医療機関としての役割や対象となる医療圏の違いから、基幹型、地域型、連携型の3つに分けられています。
鹿児島県ではこれまで9つの地域型と2つの連携型が稼働しておりましたが、この度、当院は鹿児島県から基幹型の指定を受け、令和4年9月1日より稼働を開始致しました。
基幹型認知症疾患医療センターについて
基幹型認知症疾患医療センターは、活動圏域を都道府県全域としており、都道府県内の地域型・連携型センターの取りまとめを行うなど、認知症医療の中心的役割を担うことが期待されています。
当院は、令和4年9月1日より、鹿児島県から基幹型センターの指定を受けました。当センターは、県内唯一の基幹型センターであり、鹿児島県全体における認知症疾患の保健医療水準の向上を目的に、保健・医療・福祉と連携を図りながら下記の対応を行います。
① より専門的な検査や判断を必要とする患者の鑑別診断
- 原則として地域型・連携型センターなどからご紹介いただいた患者の鑑別診断を行います。若年性認知症が疑われる方や認知症かどうかの判断が難しい方、地域型・連携型センターなどで鑑別困難な認知症の方などが主に対象となります。
- 相談員によるご本人・ご家族との面談、専門医の診察、公認心理師による心理検査、頭部MRIなどの各種画像検査などにより鑑別を行い、診断結果に基づき治療方針の検討を行います。
- 基本的にはご紹介頂いた地域型・連携型センターなどに診察結果をお伝えしお戻し致しますが、ご本人・ご家族からの認知症に関する医療相談に対応し、認知症の診療を行っている医療機関等の紹介を行う場合もあります。
② 認知症に関する地域連携推進
- 県内の連携体制強化のため、鹿児島県と協力し、県内の認知症に関する支援体制作りを推進します。
- 鹿児島県と協力し、認知症医療に関する情報発信、認知症に関する理解を促す普及啓発等を行います。
- 鹿児島県内の地域型・連携型センターとの研修会を定期的に開催し、鹿児島県内の認知症診療、認知症対策の水準の向上を図ります。
- 研修会等を通して医療従事者に対する支援者支援を行います。
③認知症に関する相談業務の実施
- 基幹型センターとして、鹿児島県内の地域型・連携型センター、関係機関(市町村、地域包括支援センター、保健所等)への相談対応を行います。
医師紹介
医師・技師紹介
※専門外来は、初診・再診どちらも曜日指定があります。
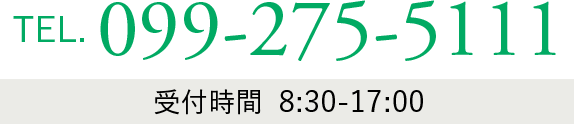
 HOME
HOME 病院紹介
病院紹介 受診される方へ
受診される方へ 医療関係者の方へ
医療関係者の方へ 診療科案内
診療科案内 部門案内
部門案内 よくある質問
よくある質問 お問合せ
お問合せ アクセス・駐車場
アクセス・駐車場